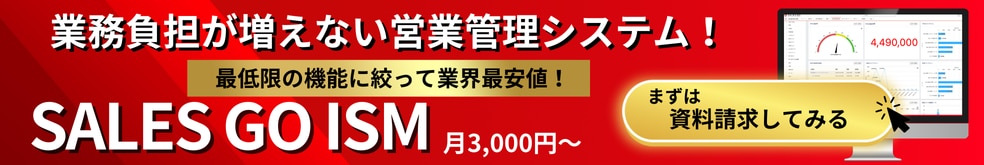展示会後のフォローを成功させるポイントとは?事前準備や手法も紹介
展示会への出展は、新規顧客獲得や売上向上を目指す上で重要なマーケティング施策ですが、当日だけで成果を上げるのは困難です。展示会の真の価値は、収集した名刺や接触した見込み客に対する適切なアフターフォローにあります。今回は、展示会のアフターフォローを成功させるためのポイントを解説します。
目次[非表示]
展示会はアフターフォローが重要!

展示会の本来の目的は、商談に繋がるリードを獲得することです。しかし展示会当日は、来場者は数多くのブースを回るため、1社あたりに割ける時間が限られています。そのため、その場での商談だけで十分な成果を上げることは現実的ではありません。
展示会後のフォローは、リードの確度を見極め、興味・関心を持つ来場者に継続的なアプローチを行うための重要な起点となります。適切なタイミングでアフターフォローを実施することで、展示会起点の商談創出や受注獲得を大幅に増加させることが可能です。
特に重要なのは、アプローチまでの時間です。時間が空いてしまうと見込み客の意欲は急速に低下してしまうため、迅速な対応が求められます。
展示会のアフターフォローの主な手法

展示会のアフターフォローには複数の手法があり、見込み客の興味関心度合いや購買検討フェーズに応じて使い分けることが効果的です。
メール
メールは一度に多くの顧客と接点を持てるため、展示会後の基本的なフォロー手法として広く活用されています。
サンクスメールでは展示会でブースにご来場いただいたお礼を伝え、製品資料やセミナー情報へのリンクを含めることで次のアクションに誘導します。
個別メール(セグメントメール)では、顧客の業界や興味関心、担当者の役職などのセグメントに合った内容を配信することで、より効果的なアプローチが可能です。
また、定期的なメルマガ配信により、中長期的なコンテンツナーチャリングを行い、見込み客との継続的な関係構築を図ることができます。
電話
電話でのフォローは、展示会では時間が限られていたヒアリングを後日じっくりと行うことで、顧客の真のニーズや課題を把握できる貴重な機会です。
展示会当日の短時間では聞けなかった詳細な状況や悩みを確認し、自社ソリューションとのマッチングを正確に判断できます。
ただし、すべての見込み客に電話をかけるのは非現実的なため、商談化の可能性が高い対象に絞って実施することが重要です。
DM
紙のDMはEメールよりも開封率や行動喚起率が高く、本人宛で74.3%という高い開封・閲読率を誇ります。手間とコストはかかりますが、その分メールよりも丁寧な印象を与え、特別感を演出できます。
DMの物理的な存在感により、デジタル疲れしている顧客にも効果的にアプローチでき、手元に残るため、継続的な認知効果も期待できます。
ただし、費用対効果を考慮し、案件化の可能性が特に高い見込み客に限定して活用することが推奨されます。
出典:一般社団法人 日本ダイレクトメール協会「DMメディア実態調査2024」
SNS
ブースでX(旧Twitter)やFacebookのフォローキャンペーンを実施することで、中長期的なリレーションシップ構築の基盤をつくることができます。
SNSを一度フォローしてもらえれば、まだ購買の見込みが低い顧客にも定期的にアプローチできる有効な手段となります。
SNSを通して魅力的なコンテンツやキャンペーン情報を継続的に発信することで、自社への関心を徐々に高め、将来的な商談機会の創出につなげることが可能です。
特に展示会という特定業界への関心が高い来場者は、その後のフォロー解除率が低い傾向にあります。
展示会のアフターフォローにおける事前準備
効果的なアフターフォローを実現するためには、展示会前の入念な準備が不可欠です。事前準備を怠ると、せっかくの見込み客との接点を活かしきれない結果となってしまいます。
ここでは、展示会のアフターフォローでしておくべき事前準備について紹介します。
事前準備1:手法の選定
誰がどうやってフォローを行うか、事前に決めておくことが重要です。営業チーム、マーケティングチーム、インサイドセールスチームなど、それぞれの役割分担を明確化し、フォロー手法もあわせて決定します。
手法の選定は、展示会で掲げている目標やかけられる予算、人的リソースとの兼ね合いで決めるようにしましょう。
限られたリソースを最大限活用するため、優先度の高い見込み客には手厚いフォローを、それ以外には効率的な手法を選択するなど、戦略的なアプローチが求められます。
事前準備2:コンテンツの用意
フォローメールに掲載するWebコンテンツ、来場者へのお礼状、製品資料、事例集など、活用するコンテンツを事前に準備しておく必要があります。これらのコンテンツは来場者の興味を失わせないもの、購買意欲を高めるためのものでなければなりません。
また、展示会当日にヒアリングシートやアンケートを用意し、フォローに必要な情報を効率的に収集することも重要です。
BANT条件(Budget、Authority、Needs、Timeframe)を踏まえた質問項目を設定し、短時間で回答してもらえるようチェック式で作成しましょう。
事前準備3:フォローのシナリオ作成
場当たり的なアフターフォローでは高い効果を期待できないため、事前に詳細なシナリオを作成しておくことが大切です。来場翌日にお礼メールを配信し、その2日後にフォロー電話をかけるといった具体的なタイムラインを設定します。
お礼メールの内容や電話をかける際のトークスクリプトも事前に準備し、一貫性のある質の高いフォローアップを実現します。
また、見込み客のセグメント別に異なるシナリオを用意し、それぞれに最適化されたアプローチを行うことで、フォロー効果を最大化できます。
展示会のアフターフォローを成功させるためのポイント

アフターフォローの効果を高めるためには、戦略的なアプローチと継続的な改善が重要です。以下のポイントを押さえることで、展示会投資のROIを大幅に向上させることができます。
ポイント1:迅速な初回連絡の実施
展示会終了直後、できれば翌日中にお礼メールや資料送付を行い、記憶が鮮明なうちに接点を維持しましょう。来場者は複数のブースを回っているため、時間が経つほど自社の印象は薄れてしまいます。
迅速な対応を実現するためには、名刺のデジタル化、メールテンプレートの準備、送信リストの事前設定など、展示会前からの周到な準備が不可欠です。
展示会当日中に名刺情報をデータ化し、翌日の午前中にはお礼メールを配信できる体制を整えておくことが成功の鍵となります。
ポイント2:来場者情報をもとにしたリストの仕分け
来場時に獲得した名刺情報やヒアリング情報をもとに、購買検討フェーズに応じてリストを仕分けることが大切です。これにより優先的にフォローすべき見込み顧客の特定と、購買検討フェーズに応じたアプローチの実施が可能になります。
見込み客を「情報収集中」「検討中」「導入直前」などのフェーズに分類し、それぞれに最適なフォローアップ内容と接触頻度を設定します。
例えば、導入直前の顧客には即座に営業担当からの電話フォローを、情報収集段階の顧客には定期的なメルマガ配信を行うなど、段階的なアプローチを実施します。
ポイント3:購買フェーズに応じたアプローチの実施
各購買フェーズの見込み客に対して、どの手法でどのような情報を提供するかを明確に決めておくことも重要です。
認知段階では業界動向や課題解決のヒント、検討段階では具体的な製品情報や事例、決定段階では導入支援や特別提案など、フェーズに応じた最適なコンテンツを提供します。
一律のアプローチではなく、顧客の状況に合わせたパーソナライズされたコミュニケーションを心がけることで、より高い成約率を実現できます。
ポイント4:中長期的に実施する
アフターフォローは一回限りではなく、継続的に見込み顧客を育てていく必要があります。定期的なメルマガや無料セミナー案内などを通じて、長期的な関係構築と商談獲得につなげる中長期的なナーチャリング戦略が重要です。
また、定期的にPDCAサイクルを回すことで、フォロー手法の効果測定と継続的な改善を行い、より高い成果を追求していくことが可能になります。
展示会への投資を無駄にしないためにも、年単位でのリレーションシップ構築を視野に入れた取り組みが求められます。
ポイント5:ツールを活用する
収集した名刺やアンケート情報を手作業で管理していると、フォローが遅れたり、重要な見込み客を見落としたりするリスクがあります。
その場合は、SFA(営業管理システム)やCRM(顧客管理システム)などのツールを活用することが効果的です。これらのツールを使うことでデータを一元管理できるほか、関心度や属性別にセグメント分けができるため、効率的なアプローチが可能になります。
さらに、MAツールを活用すれば、メール配信の自動化や開封率の測定により、見込み客の反応を把握しながら戦略的にフォローできます。
結果として、限られた時間でより多くの見込み客に適切なアプローチができ、成約率の向上につながります。
まとめ
展示会の真の価値は当日の接触ではなく、その後のアフターフォローにあります。見込み客の興味が薄れる前に迅速な初回連絡を行い、メール・電話・DM・SNSなど複数の手法を組み合わせて継続的にアプローチすることが重要です。
事前に手法選定・コンテンツ準備・フォローシナリオを策定し、来場者情報をもとに購買フェーズ別のリスト分けを実施して、それぞれに最適化されたコンテンツを提供しましょう。SFAやMAツールを活用した効率的な管理により、中長期的なナーチャリングを実現できます。
営業活動の効率化を図るなら「SALES GO ISM」の導入をご検討ください。
「SALES GO ISM」は、営業活動で本当に必要な機能のみを搭載した営業管理システムです。データを入力するだけで、フェーズのパイプラインや予実状況など数値がすぐに可視化されるため、営業方針を迅速に決定できます。
また、商談、商材、企業、担当者の4つのフェーズでさまざまなデータを管理でき、顧客にアプローチすべきタイミングも明確になるため、売上向上に寄与できます。
見込み客のアフターフォローを効率化したい企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。