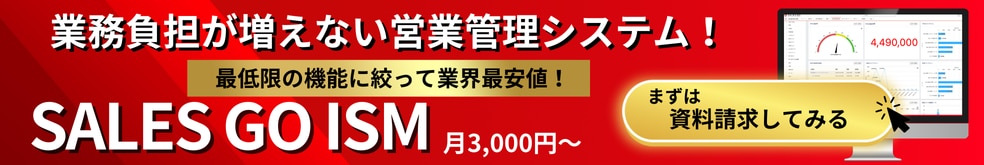手紙で心をつかむ!営業活動における手紙のメリットと活用法
テレアポやメールなどの方法を中心に営業活動を行っていても、あまり成果が出ないこともあるでしょう。そのような場合には、アナログ施策の営業手紙を導入する方法もあります。
ただ、実際に導入する際には、効果を把握し自社の業種や商材に合うかどうか見極めた上で決めることが大切です。今回は営業手紙について、効果や押さえるべきポイント、注意点などを解説し、例文も紹介します。
目次[非表示]
- 1.営業手紙の効果とは?
- 1.1.物理的に届く
- 1.2.目立つ
- 1.3.決裁権者に届く可能性がある
- 2.営業手紙を書く際に押さえるべきポイント
- 2.1.冒頭には挨拶文を書く
- 2.2.用件は読みやすく端的に書く
- 2.3.営業手紙を出すタイミング
- 2.4.営業手紙は手書きで作成
- 3.営業手紙の例文
- 3.1.新規顧客を開拓する場合
- 3.2.既存顧客に送る場合
- 4.営業で手紙を書く際の注意点
- 5.まとめ
営業手紙の効果とは?

最初に営業手紙でどのような効果が期待できるのか見ていきましょう。
物理的に届く
手紙は実物が物理的に相手に届きます。すぐに開封して読まなくても、実物が残るため、届いた後は何度も目にする機会があるでしょう。メールの場合には見落としたまま埋もれてしまうこともよくありますが、手紙の場合にはそのようなことはありません。
また、昨今では手紙でやり取りする機会は少ないため、印象に残りやすいのもメリットです。メールだと届いたときに忙しくて読む時間がなかったら、その後も読んでもらえる見込みは薄いでしょう。しかし、手紙なら時間が経過してからでも読んでもらえる可能性は十分にあります。
目立つ
メールで営業活動をしている企業は多いため、顧客のところにはさまざまな企業から大量にメールが届きます。自社で送付したメールが埋もれてしまって、届いていたことすら認識してもらえないこともあるかもしれません。
これに対して、本人宛に手紙が届く機会は少ないため、営業手紙は目立ちます。開封してもらえる確率も高く、丁寧に目を通してもらえるでしょう。
決裁権者に届く可能性がある
営業では、決裁権者と直接やり取りできるかどうかが重要です。メールだと営業先の社員に目を通してもらえたとしても、決裁権者までは届いていないこともあるでしょう。テレアポや飛び込み営業なども、あまり権限のない社員が対応するケースがほとんどです。
これに対して、営業手紙は決裁権者に直接届きやすいのがメリットです。決裁権者が直接開封して読むのであれば、訴求効果も高いといえます。興味を持ってもらえれば、その後の商談や成約などのプロセスもスムーズにいくでしょう。
営業手紙を書く際に押さえるべきポイント

営業手紙を効果的なものにするためには書き方が重要です。ここでは、営業手紙を書く際に押さえておくべきポイントを見ていきましょう。
冒頭には挨拶文を書く
営業手紙の冒頭には、挨拶文を記載するのが一般的です。最初に「拝啓」という頭語を記し、続けて時候の挨拶を述べます。その後、「貴社におかれましては~」のように、相手の状況を気遣う表現を添えるのが適切です。
時候の挨拶とは、季節にちなんだ定型表現のことで、季節ごとに代表的な言い回しがいくつか存在します。季節ごとの代表的な表現は次の通りです。
・春:桜花の候、春暖の候、新緑の候、梅雨の候
・夏:盛夏の候、猛暑の候、残暑の候、初秋の候
・秋:秋冷の候、霜降の候、晩秋の候、深秋の候
・冬:小寒の候、大寒の候、余寒の候、初春の候
これらのうち、現在の季節に合った表現をひとつ選び、文書の冒頭に使用しましょう。結びには「敬具」などの結語を用いますが、これは冒頭の「拝啓」と対になる表現です。文の形式を整えるため、冒頭と結びの言葉はセットで使用するようにしましょう。
用件は読みやすく端的に書く
相手は忙しい中、時間を割いて手紙を開封して読んでくれています。そのような事情を考慮し、あまり長々とした文章になってしまわないように注意が必要です。
相手に配慮し、用件はわかりやすく端的にまとめて書くようにしましょう。
記載する順番としては、前文の挨拶の次には手紙を送った経緯を記載し、次に手紙の目的を記載すると、スッキリまとまります。その後に、具体的な用件を記載しましょう。
営業手紙のため、商品やサービスの訴求が目的ですが、詳細な説明を記載するのはあまり良くありません。どうしても長くなってしまい、相手にとってわかりづらいと感じることもあるでしょう。
そのため、商品やサービスそのものの説明は、簡単な内容にとどめておき、相手にとっての導入メリットを明確に伝えることが大切です。
詳細な説明は商談のアポイントが取れてから行うようにしましょう。
営業手紙を出すタイミング
営業手紙を出すタイミングは、テレアポの後や新規開拓営業時などが効果的です。
テレアポの場合には、相手の反応が見えにくく、あまり印象に残らないこともあるかもしれません。後からお礼の手紙を送れば感謝の気持ちを伝えられて、印象に残せます。
新規開拓営業時にも、訪問後に手紙を送ると印象に残りやすく信頼関係の構築につながりやすいです。
初回訪問後や商談後などに営業手紙を送るのも、効果的なタイミングです。相手への配慮を示すことで特別感を与えられ、関係構築にもつながります。初回訪問後なら顧客との距離を縮める助けとなり、商談後なら、次のコミュニケーションへとつなげるきっかけをつくれます。
さらに契約成立後にも営業手紙を送れば、感謝の気持ちを示せて、長期的な信頼構築につなげられるでしょう。
営業手紙は手書きで作成
営業手紙で最初に直面する課題は「封筒を開けて読んでもらうこと」です。封筒の宛名や住所などが手書きなら特別感があり開封されやすいでしょう。手紙の本文も手書きだと、より大きな特別感を与えられます。
ただし、すべてを手書きにするのは負担が大きく、現実的でない場合もあります。そのような場合には、封筒だけを手書きにするのがおすすめです。
営業手紙の例文

新規顧客開拓と、既存顧客に送る場合に分けて、営業手紙の例文を見ていきましょう。
新規顧客を開拓する場合
拝啓 大寒の候、貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
突然のご連絡、失礼いたします。
私は、○○株式会社の○○と申します。
貴社のホームページを拝見し、業務効率化やコスト削減において、弊社がお役に立てるのではないかと考え、僭越ながらご連絡差し上げました。
弊社では「○○」というサービスを提供しております。これまでに当サービスを導入していただいた企業様では、最大○%のコスト削減を実現した実績がございます。
貴社の事業においても同様にお役に立てると考えております。
つきましては、ぜひ一度ご挨拶、ご提案の機会を頂戴できましたら幸いです。
もし、ご興味をお持ちいただけましたら、お電話やメールでお知らせいただけますと幸いです。
ご多用のところ恐縮ではございますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
敬具
既存顧客に送る場合
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、このたび弊社では、〇月にリリースを予定している新サービス「××」につきまして、ぜひ○○様とお会いした上で詳細をお伝えさせていただきたく、本書をお送りいたしました。
本サービスは、○○業務を代行することで、業務の効率化やコストの削減を支援するものです。ご導入いただくことで、貴社における○○作業の工数を大幅に削減できる可能性がございます。
ご多用のところ誠に恐縮ではございますが、〇月〇日〇時ごろ、弊社の○○よりご連絡差し上げますので、その際にご面談の可否につきましてお返事をいただけますと幸いに存じます。
敬具
営業で手紙を書く際の注意点
手紙の枚数は適切なバランスが重要です。手紙の枚数が1~2枚では商品やサービスを訴求する内容を十分に盛り込むのが難しい一方、5~6枚だと相手にとって心理的負担になってしまいます。そのため、3~4枚程度にするのが良いでしょう。
また、営業しすぎる内容だと、拒絶反応につながってしまう可能性があります。あまり営業色を前面に出すのではなく、商品やサービスの価値を伝えることが大切です。
その上で相手にとって得られるメリットを提示すれば、興味を持ってもらえる可能性が高まります。
まとめ
営業手紙は実物が物理的に残り、目立つため、メールよりも開封されやすい傾向にあります。決裁権者に読んでもらえる可能性が高いのもメリットです。営業色を出しすぎず、価値を伝えるような内容で、3~4枚に収まる文章量で記載しましょう。
新規開拓にお悩みであれば、SALES GO ISMの導入をご検討ください。営業活動で本当に必要な機能のみを搭載しており、案件の進捗状況や顧客情報、営業担当者のタスクを一元管理することが可能です。
顧客台帳を更新する感覚で誰でも直感的に利用でき、データを入力するだけで営業活動の状況が可視化されるため、営業方針の決定もスムーズになります。
また、フェーズの設計や必要項目はSALES GO ISMが作成し、営業戦略から商談獲得まで徹底サポートしております。
営業活動を効率化し、受注獲得をスピーディーに進めたい企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。